【概 要】
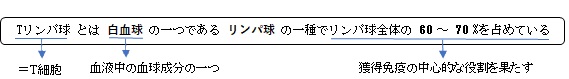
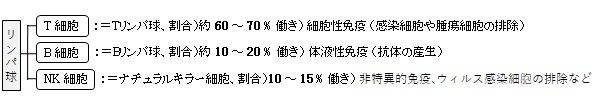

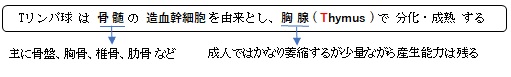
・胸腺で分化・成熟したものを「ナイーブT細胞」と呼び、血流にのってリンパ節や脾臓などの二次リンパ器官に運ばれる。
・二次リンパ器官で抗原提示を受けて活性化され分裂・分化をし、その場で働くか一部は血流に乗って全身の末梢神経に移動する。
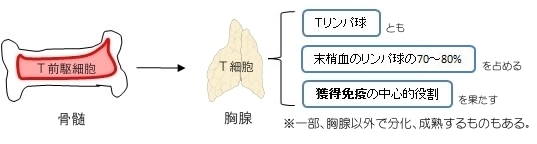
⇒ 造血幹細胞の分化の模式図
【分 化】
以下T細胞の分解について簡単に記す。
〈骨髄において〉
1. 造血幹細胞から共通リンパ系前駆細胞になる。
※造血幹細胞は全ての血球の元になる細胞で、共通リンパ系前駆細胞はリンパ球系の元になる細胞。
2. 共通リンパ系前駆細胞からT細胞前駆細胞になる。
〈血流に乗って胸腺へ移動〉
3. 胸腺の皮質において未熟T細胞となる。
この段階では「CD4⁻CD8⁻」⇒T細胞の表面にある タンパク質(細胞膜のマーカー)は発現せず。
4. T細胞受容体(TCR)の再構成
遺伝子再構成により、個々のT細胞が固有のTCRをもつようになる。
5. 陽性選択(positive selection)
自分のMHC分子を認識できる細胞だけが生き残る(胸腺皮質で実施)。
このとき、CD4⁺ または CD8⁺ のどちらかに決まる。
6. 陰性選択(negative selection)
自己抗原を強く認識する細胞は除去される(胸腺髄質で実施)。
自己免疫を防ぐための重要な過程。
7. 成熟T細胞(naïve T cell)
自己MHCを弱く認識する適切なT細胞だけが残る。
〈胸腺を出て末梢リンパ器官(リンパ節・脾臓など)へ移動。〉
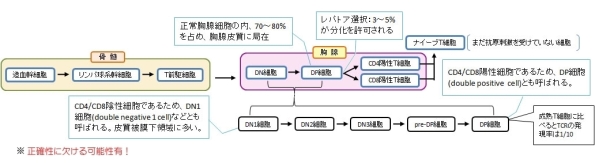
【種 類】
T細胞はその細胞膜表面に発現する細胞マーカーによって分類され、その細胞マーカーはCD番号で整理されている。(CD=cluster of differentiation) そして、それぞれの細胞によって働きが異なる。
| |
名 称 |
解 説 |
1 |
|
|
2 |
キラーT細胞 |
|
3 |
|
suppressor T cell
日本人が発見し、免疫反応を抑制し、終了に導く細胞ということで一時期盛んに研究の対象となったが、現在ではその存在自体が疑問視されている。
|
4 |
レギュラトリーT細胞 |
regulatory T cell = 制御性T細胞、調節性T細胞
免疫を抑制(T細胞の活性化を抑制)する機能に特化した細胞で、自己免疫疾患を防いでいる。以下の2種類がある。
内在性のもの:胸腺内で自然発生したもの
誘導性のもの:末梢血中のナイーブT細胞から分化、誘導されたもの
|
5 |
NKT細胞 |
natural killer T cell
ナチュラルキラー細胞とT細胞の両方の要素を併せ持つ細胞。⇒ 詳細ページ
|
6 |
γδ型T細胞 |
gamma -delta T cell
T細胞の表面にあるT細胞受容体(TCR)には「αβ型」と「γδ型」の2種類がある。末梢血中のほとんどのT細胞は「αβ型」だが、「γδ型」も数%存在している。
αβ型のT細胞受容体が「MHCクラス分子+抗原ペプチド」を認識するのに対して、γδ型はイソペンテニルピロリン酸(IPP)とMHC class Ⅰ related chain A/B(MIC A/B)を認識する。
⇒ 参考サイト
|