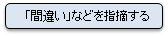【概 要】
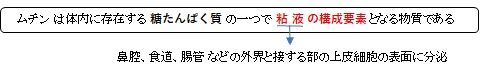
・粘液は以下のように細胞から分泌されたムチンに水分(大部分を占める)とその他の要素が加わって形成される。
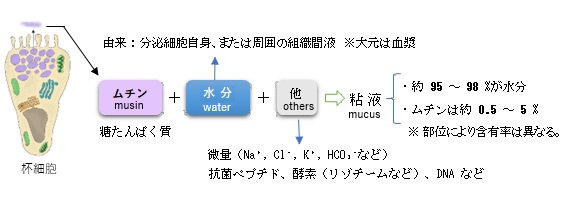
【ムチンの種類】 参考:「ChatGPT」
以下、「ChatGPT」を参考にムチンの種類を一覧にしてみたが、その全てが挙げられているかどうかは不明。
| |
名 称 |
分布・特徴 |
1 |
MUC2 |
腸(特に大腸)で主に発現。腸内細菌と腸壁のバリア形成 |
2 |
MUC5AC |
胃・気道上皮。ゲル状粘液を形成。 |
3 |
MUC5B |
唾液腺、気道腺。粘度が高く、持続的なバリアを形成。 |
4 |
MUC6 |
胃の幽門部などで分泌される。酸から粘膜を守る。 |
5 |
MUC1, MUC4, MUC16など |
細胞膜結合型ムチン。細胞表面の保護・情報伝達に関与 |
【ムチンを分泌する主な細胞】
以下粘液を分泌する細胞を簡単に一覧にしたものになる。参考:ChatGPT
| |
細胞名 |
主な分布 |
特徴・分泌物 |
1 |
杯細胞 |
消化管上皮(特に小腸・大腸)、呼吸器上皮 |
単細胞でムチン(mucin)を分泌。PAS染色陽性。上皮中に散在。 |
2 |
粘液腺細胞 |
唾液腺(顎下腺の一部、舌下腺など)、気道腺 |
多細胞腺を構成。白っぽく泡状の細胞質でムチンを分泌。核は基底部に扁平。 |
3 |
子宮頸部腺細胞 |
子宮頸部粘膜 |
子宮頸管粘液を分泌。排卵期と黄体期で粘度が変化。 |
4 |
Brunner腺細胞 |
十二指腸の粘膜下層 |
アルカリ性粘液を分泌して胃酸から腸壁を保護。 |
5 |
副鼻腔・鼻腔の粘液細胞 |
鼻腔、上気道粘膜 |
粘液で吸入空気中の異物・微生物を捕捉。杯細胞と腺が連携。 |
【ムチンが分泌される主な場所】
以下粘液が分泌される場所を簡単に一覧にしたものになる。参考:ChatGPT
| |
場 所 |
主な働き |
分泌細胞 |
1 |
呼吸器(鼻腔〜気管・気管支) |
異物・病原体の捕捉と排除(線毛運動で外へ) |
杯細胞、気道腺細胞 |
2 |
消化管(口腔〜肛門) |
潤滑・酸や消化酵素から粘膜保護・機械的刺激の緩和 |
杯細胞、表層粘液細胞、腸腺 |
3 |
眼(結膜、涙液) |
乾燥防止・異物排除 |
杯細胞(結膜)、涙腺のムチン産生細胞 |
4 |
耳(中耳、耳管) |
粘膜保護・細菌の侵入防止 |
杯細胞、腺細胞 |
5 |
生殖器(膣・子宮頸管など) |
潤滑・感染防御・精子移動の調整 |
頸管腺細胞、腟上皮細胞 |
6 |
泌尿器(尿道、膀胱) |
尿による刺激・感染からの保護 |
杯細胞、尿道腺など |
7 |
胆道・膵管などの一部導管系 |
粘液で内容物の流れを滑らかにし、上皮を守る |
粘液細胞(胆管、膵管) |
【ChatGPTに聞いてみた】
Q:「ムチンの80~90%は糖なのにタンパク質なのか?」
A:「ムチンは「タンパク質に大量の糖が付いた構造」ですが、それでも「糖タンパク質(glycoprotein)」と分類されます。
つまり、「糖が主体に見えるほど多くても、あくまでタンパク質が“軸”で、そこに糖鎖が付加された構造」なのです。
- 骨格(主構造)はタンパク質
- その表面に多数の糖鎖(O-glycan)が密集して装飾されている
- 糖鎖が全体重量の80~90%を占めることもあるが、構造のベースはタンパク質
- 糖鎖は外部環境との相互作用・保護・粘性に関与 」
Q:「ムチンは分子量的にはタンパク質よりも糖の方が多いのか?」
A:「ムチンでは、全体の分子量のうちおよそ80~90%が糖鎖の分子量であり、タンパク質部分は10~20%程度に過ぎない。」
詳しい説明
ムチンの構造概略:
- 骨格:タンパク質の主鎖(core protein)
- 修飾:その主鎖のセリン(Ser)やスレオニン(Thr)残基に、多数のO型糖鎖が付加される
- 糖鎖の構成:N-アセチルガラクトサミン(GalNAc)を起点とする糖鎖に、ガラクトース、フコース、シアル酸などが枝分かれして構成される
数値的イメージ
| |
項 目 |
ムチン |
一般的な糖タンパク質(例:IgGなど) |
1 |
分子量(全体) |
1,000,000~20,000,000 Da
(1–20 MDa) |
30,000~150,000 Da
(30–150 kDa) |
2 |
糖の割合 |
80~90% |
通常は 10%以下 |
3 |
タンパク質の役割 |
骨格(糖鎖の土台) |
主構造+機能発現 |
なぜ糖が多いのか?
- ムチンは粘液を構成し、粘度・潤滑性・バリア機能を発揮する必要があるため、多数の親水性の糖鎖が必要
- ムチンのO型糖鎖はブラシ状にびっしりと並び、水分を保持し、粘性ゲルを形成