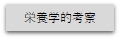
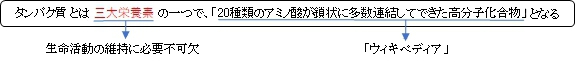
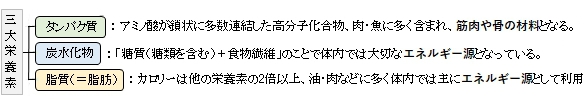
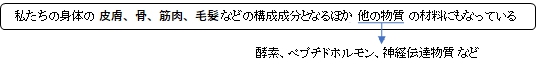
・体重の約20%を占めていて、水の次に多い物質。
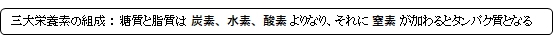
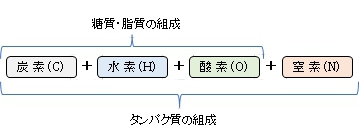

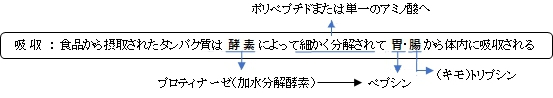

【タンパク質を多く含む食品】
以下はタンパク質を多く含む食品の例となる。「単位(g)」の数字は食品100あたりのタンパク質の量を表す。
| |
食品名 |
単位(g) |
|
食品名 |
単位(g) |
1 |
まぐろ(赤味) |
28.3 |
6 |
真鯛 |
19.8 |
2 |
かつお |
25.8 |
7 |
鶏むね肉 |
19.7 |
3 |
鶏ささみ肉 |
24.0 |
8 |
和牛ヒレ |
19.5 |
4 |
プロセスチーズ |
22.7 |
9 |
アジ |
18.7 |
5 |
豚モモ肉 |
20.4 |
10 |
和牛サーロイン |
16.9 |
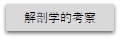

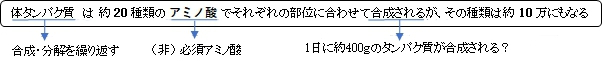
・2013年12月16日付の朝日新聞の記事の「迫れ、細胞リサイクル(病気の解明に期待 研究進む)」に以下のような解説が掲載されていた。
「呼吸や栄養の消化など、あらゆる生命の営みにたんぱく質は欠かせない。このため生物は常に大量のたんぱく質を体内で合成している。人間は、毎秒300万個のペースで作る赤血球をはじめ、1日に約400グラムのたんぱく質を作る。食事で補給するたんぱく質は1日80~90グラム。残りは不要になったり、壊れたりしたたんぱく質をリサイクルして補っている。その役割を担うのがオートファジーだ。」

【タンパク質の利用】
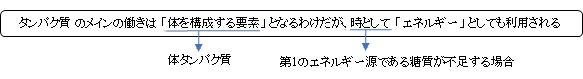
・体内でのエネルギー源ともなるタンパク質であるが、摂取しすぎると脂肪として体内に蓄積される。
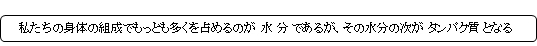
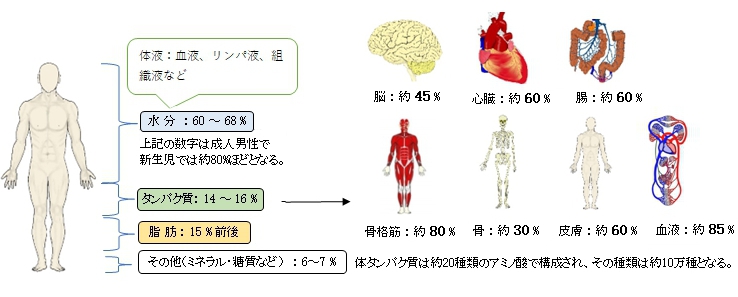
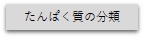
タンパク質の分類には以下のようなものがある。
■構成成分による分類■
分類名 |
内 容 |
例 |
純タンパク質 |
アミノ酸のみからなる |
アルブミン、グロブリン |
複合タンパク質 |
タンパク質 + 非タンパク質成分 |
ヘモグロビン(ヘム付き) |
1 |
糖タンパク質 |
糖鎖が付加 |
IgG、ムチン |
2 |
リポタンパク質 |
脂質が付加 |
HDL、LDL |
3 |
クロモタンパク質 |
色素が結合 |
ヘモグロビン |
4 |
ヌクレオタンパク質 |
核酸と結合 |
ヒストン、リボソーム |
5 |
金属タンパク質 |
金属イオンを含む |
フェリチン、亜鉛フィンガー |
6 |
リンタンパク質 |
リン酸基が付加 |
カゼイン、酵素類 |
■立体構造による分類■
|
分類名 |
内容 |
例 |
1 |
繊維状タンパク質 |
長く伸びた構造。構造支持の役割。水に溶けにくい |
ケラチン(髪)、コラーゲン |
2 |
球状タンパク質 |
丸くコンパクトな構造。酵素などの機能性が高い |
ヘモグロビン、酵素、抗体 |
3 |
膜タンパク質 |
細胞膜に埋まっている。輸送や情報伝達に関与 |
イオンチャネル、受容体 |
■機能による分類■
|
分類名 |
機 能 |
例 |
1 |
酵素 |
化学反応の触媒 |
アミラーゼ、DNAポリメラーゼ |
2 |
輸送タンパク質 |
物質の運搬 |
ヘモグロビン、トランスフェリン |
3 |
構造タンパク質 |
細胞や組織の構造を支える |
アクチン、コラーゲン |
4 |
貯蔵タンパク質 |
栄養源 |
フェリチン(鉄貯蔵)、カゼイン |
5 |
受容体タンパク質 |
シグナル受容 |
インスリン受容体 |
6 |
運動タンパク質 |
運動・収縮 |
ミオシン、キネシン |
7 |
調節タンパク質 |
遺伝子発現の調整など |
転写因子、ホルモン類 |
8 |
免疫タンパク質 |
免疫応答 |
抗体(IgGなど) |
■起源・由来による分類■
|
分類名 |
内 容 |
例 |
1 |
動物性タンパク質 |
動物に由来 |
卵白アルブミン、ミオグロビン |
2 |
植物性タンパク質 |
植物に由来 |
グリアジン(小麦)、レクチン |
■化学的性質による分類■
|
分類名 |
内 容 |
例 |
1 |
酸性タンパク質 |
酸性アミノ酸が多い |
DNA結合タンパク質 |
2 |
塩基性タンパク質 |
塩基性アミノ酸が多い |
ヒストン |
3 |
中性タンパク質 |
バランス型 |
アルブミン |